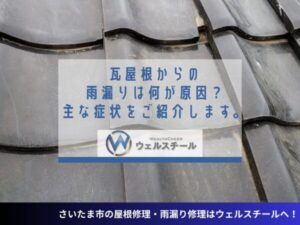雨漏りに要注意!屋根の「谷」「谷樋」とはどんな場所?
屋根の雨漏りには様々な原因がありますが、今回は特に気をつけたい「谷」や「谷樋」についてお話しします。これらは屋根の形によってできる窪みや水を流す通り道のことです。雨水がここに集まりやすいため、時間とともに傷みやすく、しっかりとお手入れをしないと雨漏りの心配が出てきます。
この記事では、「谷」「谷樋」がどのような役割を持ち、雨漏りを防ぐにはどうすれば良いのか、詳しくご説明していきます。
屋根の「谷」とは

屋根の「谷」とは、屋根面と屋根面が合流する部分にできるV字型のくぼみのことを指します。建物の設計によっては、この谷部分が複数できることもあります。特に複雑な形状の屋根では、谷の数が増えるため、それだけ雨水の流れが集中しやすくなります。
この谷部分は、屋根全体の雨水が集まる場所となるため、非常に重要な構造です。屋根の勾配によっては、谷に大量の水が流れ込み、一気に排水しなければならないため、適切な施工が求められます。もし施工不良や経年劣化によって水の流れが滞ると、水が溜まりやすくなり、雨漏りの原因となる可能性が高くなります。
また、谷部分には落ち葉やゴミが溜まりやすく、排水の妨げになることがあります。特に、周囲に樹木が多い環境では、定期的に清掃を行わないと谷部分が詰まり、水が正常に流れなくなることがあります。そのため、谷の定期的なメンテナンスが非常に重要になります。
「谷樋(たにどい)」とは

「谷樋(たにどい)」とは、屋根の谷部分に設置される板金のことを指します。谷樋の役割は、屋根の谷に流れ込んだ雨水をスムーズに排水し、屋根や建物内部への水の侵入を防ぐことです。
つまり、雨樋と同じような役割をもっていることから、谷樋と呼ばれているのです。
谷樋は、屋根の防水性能を維持するために欠かせない重要な部材ですが、長年の使用によって劣化しやすい部分でもあります。特に、金属製の谷樋はサビや腐食が進行すると穴が開き、そこから雨水が建物内に侵入することがあります。そのため、定期的な点検と適切なメンテナンスが必要になります。
谷樋に使用される代表的な材質は以下の通りです。
ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板は、アルミニウムと亜鉛の合金メッキが施された鋼板で、耐久性が高く、サビにも強いのが特徴です。現在、屋根の谷樋として最も広く使用されている材質の一つです。耐用年数が長く、メンテナンスの手間も比較的少ないため、コストパフォーマンスに優れています。
銅製の谷樋
銅製の谷樋は、高耐久で長寿命ですが、経年劣化によって表面に緑青(ろくしょう)と呼ばれる緑色のサビが発生します。緑青自体には害はありませんが、銅は年月とともに腐食が進むため、長期間使用している場合は劣化状況を確認する必要があります。
ステンレス製の谷樋
ステンレスはサビに非常に強く、耐久性が高いため、長寿命な谷樋材として利用されます。ただし、加工が難しく、コストが高めなのがデメリットです。また、屋根の素材やデザインによっては適さない場合があるため、事前に専門業者と相談することが推奨されます。
亜鉛メッキ鋼板
亜鉛メッキ鋼板は、かつて広く使用されていた素材ですが、サビが発生しやすく、耐久性の面で劣るため、現在ではガルバリウム鋼板に取って代わられています。それでもコストが比較的安価であるため、一時的な補修などで使用されることがあります。
谷樋の選び方は、屋根の材質や耐用年数、コストなどを考慮して決める必要があります。適切な材質を選ぶことで、屋根全体の耐久性を向上させ、雨漏りのリスクを減らすことができます。
また、谷樋の適切な設置には、専門的な技術が必要です。設置の際に勾配をしっかり確保し、スムーズに排水できるようにすることが重要です。施工ミスがあると、水がうまく流れずに溜まり、雨漏りや屋根の劣化を引き起こす可能性があるため、信頼できる業者に依頼することが推奨されます。
このように、屋根の「谷」と「谷樋」は、雨水をスムーズに流すために欠かせない重要な構造です。特に谷部分は雨漏りのリスクが高い箇所であるため、定期的な点検とメンテナンスを行い、適切な対策を取ることが大切です。
屋根の「谷」「谷樋」で雨漏りが発生する原因

屋根の「谷」や「谷樋」は雨水が集中する場所であり、排水機能が正常に働かないと雨漏りの原因になりやすい部分です。特に谷樋は、屋根の他の部分と比べて劣化が早い傾向があるため、定期的な点検やメンテナンスが不可欠です。ここでは、谷や谷樋で雨漏りが発生する主な原因について詳しく解説します。
経年劣化
谷樋は金属製のものが多く、長年使用することでサビや腐食が進行します。特に、雨水が溜まりやすい箇所ではサビが発生しやすく、穴が開いてしまうこともあります。以下のような状態になった場合は、谷樋の交換や修理が必要です。
- サビの発生(軽度のサビであれば補修が可能ですが、広範囲に広がっている場合は交換が必要になります。)
- 穴や亀裂(金属の腐食が進むと穴が開き、そこから雨水が漏れ出すことがあります。)
- 歪みや破損(経年劣化により谷樋が歪むと、適切な排水ができなくなり、雨水が溜まりやすくなります。)
特に施工から10年以上経過した屋根では、谷樋の劣化が進んでいる可能性が高いため、定期的な点検をおすすめします。屋根の点検を怠ると、雨漏りが発生し、建物の内部に被害が広がる恐れがあります。
ゴミや落ち葉の詰まり
谷部分には雨水が流れ込むだけでなく、風で飛ばされた落ち葉やゴミも溜まりやすい特徴があります。特に以下のような環境では、谷樋の詰まりが発生しやすくなります。
- 周囲に樹木が多い住宅(秋の落ち葉や枯れ枝が谷樋に詰まり、排水を妨げることがあります。)
- 強風が吹きやすい地域(風で飛ばされたゴミや砂ぼこりが谷樋に蓄積し、詰まりの原因になります。)
- 鳥や動物の巣作り(鳥が巣を作るために木の枝や泥を運び込み、谷樋を塞ぐことがあります。)
谷樋が詰まると、雨水がスムーズに流れず、屋根の隙間や継ぎ目から水が染み込んで雨漏りを引き起こす可能性があります。特に、長期間放置すると水が溜まった状態が続き、屋根材の腐食やカビの発生につながるため、定期的な清掃が必要です。
施工不良
谷樋の設置工事が適切に行われていない場合、雨水が正常に排水されず、雨漏りの原因になります。以下のような施工ミスがあると、谷樋の性能が十分に発揮されません。
- 取り付け角度が適切でない(谷樋は一定の勾配を確保する必要がありますが、角度が不足していると水が流れにくくなり、溜まりやすくなります。)
- 継ぎ目の処理が不十分(谷樋の接続部分が適切に密閉されていないと、継ぎ目から水が漏れることがあります。)
- 適切な防水処理がされていない(谷部分には防水シートやシーリング材を施工する必要がありますが、これが不十分だと水が浸入しやすくなります。)
- サイズや材質の選定ミス(屋根の面積や雨量に対して適切な谷樋のサイズを選ばないと、排水能力が不足してしまいます。また、適切な材質を使用しないと、劣化が早まり雨漏りのリスクが高まります。)
施工不良による雨漏りは、新築やリフォーム後に数年で発生することが多いため、施工後は定期的な点検を行い、問題がないか確認することが重要です。また、信頼できる専門業者に依頼することで、施工ミスを防ぐことができます。
気温変化や自然災害による影響
屋根の谷樋は、気温の変化や自然災害の影響を受けやすい部分でもあります。特に、以下のような要因によって劣化が早まることがあります。
- 凍結と膨張収縮(冬場に雨水が谷樋内で凍結すると、膨張して金属部分にダメージを与えます。これを繰り返すことで、ひび割れや破損が生じることがあります。)
- 台風や強風(台風や強風によって飛ばされた異物が谷樋を傷つけたり、歪ませたりすることがあります。)
- 地震の影響(地震によって屋根が歪むと、谷樋が変形し、隙間ができて雨水が漏れやすくなります。)
このような外的要因によるダメージは、事前に防ぐのが難しいため、定期的な点検を行い、早めに補修をすることが重要です。
「谷」「谷樋」の雨漏りを防ぐメンテナンス方法

屋根の「谷」や「谷樋」は、雨水が集中しやすく雨漏りのリスクが高い部分です。適切なメンテナンスを行うことで、劣化やトラブルを未然に防ぎ、屋根の寿命を延ばすことができます。ここでは、谷や谷樋の雨漏りを防ぐための具体的なメンテナンス方法について詳しく解説します。
定期的な点検と清掃
谷樋は雨水をスムーズに流すために重要な役割を果たしており、定期的な点検と清掃が必要です。まず、目視でサビや腐食、ヒビ割れ、穴あきなどの劣化の兆候を確認し、早めに補修することが大切です。また、強風や大雪の影響で歪みや固定部分の緩みが生じていないかもチェックしましょう。これらの異常を放置すると、雨水が適切に流れず、雨漏りの原因となる可能性があります。
さらに、谷樋には落ち葉やゴミが溜まりやすく、これが詰まりを引き起こすこともあります。特に、周囲に樹木が多い住宅や強風の影響を受けやすい地域では、定期的な清掃が不可欠です。長年メンテナンスをしていない住宅では、汚れが蓄積していることが多いため、一度徹底的な清掃を行うのが望ましいでしょう。
清掃方法としては、まず手作業でゴミを取り除き、その後ホースで水を流して排水の流れを確認します。ただし、高所での作業は危険を伴うため、安全対策を徹底し、必要に応じて専門業者に依頼することも検討しましょう。
防水処理の強化
谷樋の防水性能を維持するためには、防水処理を強化することが重要です。まず、谷部分に施工されている防水シートは経年劣化によって機能が低下するため、定期的に状態を確認し、必要に応じて新しいシートに張り替えることで雨漏りを防ぎます。さらに、谷樋の接合部分に使用されているシーリング材(コーキング)も、ひび割れや剥がれ、縮みが見られる場合には再施工が必要です。シーリング材の補修を適切に行うことで、谷樋の耐久性を向上させることができます。
また、防水塗料を谷樋に塗布することも効果的な対策です。これにより金属部分のサビを防ぎ、防水性能を強化できます。特に、劣化が進んでいる谷樋には有効な方法となるため、必要に応じて検討しましょう。
材質の見直しと交換
谷樋の劣化が進んでいる場合や、雨漏りを繰り返している場合は、より耐久性の高い材質に交換することを検討しましょう。現在、谷樋には以下のような材質が使用されています。
① ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板は耐久性が高くサビに強い材質で、比較的安価で施工がしやすく、メンテナンスの負担も少ないという利点があります。ただし、経年劣化によって細かいサビが発生する可能性があるという欠点もあります。
② 銅
銅は長寿命で耐久性が高いのが特徴です。特に、経年変化によって発生する緑青(ろくしょう)が防錆効果を持ち、錆びにくいというメリットがあります。しかし、その一方で価格が高く、酸性雨の影響を受けやすいというデメリットもあります。
③ ステンレス
ステンレスはサビに強く、耐候性に優れているのが特徴です。長期間使用できるためメンテナンスの手間が少ないというメリットがありますが、初期コストが高く、施工時に特殊な技術が必要になる点がデメリットとして挙げられます。
④ 樹脂製の谷樋
樹脂製の谷樋は軽量で耐久性があり、サビの心配がなく比較的安価なのがメリットです。しかし、紫外線による劣化が早く、定期的な交換が必要になるというデメリットがあります。
プロによる点検・修理の重要性
谷や谷樋のメンテナンスは高所作業が多く危険を伴うため、安全面を考慮し、定期的にプロの屋根業者に点検を依頼することが重要です。プロによる点検では、劣化やサビの進行状況、雨漏りの兆候、施工不良や不具合の有無を確認できます。修理や交換のタイミングとしては、施工から10年以上経過している場合や、サビや穴あきが見られる場合、何度も雨漏りが発生している場合が挙げられます。
雨漏りが発生した場合の対処法

屋根の「谷」や「谷樋」で雨漏りが発生した場合、迅速な対応が求められます。放置すると雨水が室内に侵入し、建物の構造や内装に深刻なダメージを与える可能性があります。ここでは、雨漏りが発生した際の応急処置や、専門業者に依頼する際のポイントについて詳しく解説します。
応急処置の方法
雨漏りが発生した際、専門業者に修理を依頼するまでの間にできる応急処置を行うことで、被害を最小限に抑えることが可能です。以下の方法を試してみましょう。
① 防水テープで一時的に水の侵入を防ぐ
雨漏りの原因箇所が特定できる場合は、市販の防水テープを使用して一時的に水の侵入を防ぐことができます。
使用方法
①濡れている部分をできる限り乾かす
②防水テープをしっかりと貼る
③雨水が入らないか確認する
注意点
- あくまで一時的な対策であり、根本的な修理にはならない
- 屋根の上での作業は危険なので、無理に登らない
② バケツやブルーシートを活用する
室内に水が漏れてきている場合は、バケツを設置して水滴を受け止めることで床や家具の被害を防ぐことができます。また、広範囲に水が広がる場合はブルーシートを敷くと効果的です。
バケツの活用ポイント
- 水の飛び散りを防ぐため、バケツの底に雑巾やタオルを敷く
- 溜まった水はこまめに捨てる
ブルーシートの活用方法
- 天井からの雨漏りが激しい場合、天井に近い場所に広げて固定する
- 壁沿いから水が伝ってくる場合は、床に敷いて壁の下部分を覆う
③ 室内の湿気対策をする
雨漏りによって湿度が上がると、カビや腐食の原因になります。可能であれば以下の対策を行いましょう。
- 換気をする
- 除湿機を使用する
- タオルや新聞紙で水を拭き取る
専門業者に依頼する際のポイント

雨漏りの応急処置をした後は、できるだけ早く専門業者に修理を依頼しましょう。業者選びの際には、以下のポイントをチェックすることが重要です。
迅速に対応できるかどうか
雨漏りは放置すると建物へのダメージが進行するため、できるだけ早く修理することが重要です。業者を選ぶ際は、緊急対応の有無、現地調査や見積もりまでの対応スピード、修理までの工期を確認しましょう。特に梅雨や台風シーズンは予約が埋まりやすいため、早めに連絡することをおすすめします。
適正な見積もりを出してくれるか
適正な料金で修理を行うために、業者からの見積もり内容をしっかり確認することが大切です。工事内容の詳細、使用する材料の種類、工期の目安、追加費用の有無を確認し、予想外の出費を防ぎましょう。特に、極端に安い見積もりを提示する業者は手抜き工事のリスクがあるため注意が必要です。また、1社だけでなく複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を判断しやすくなります。
過去の施工実績や口コミを確認する
信頼できる業者を選ぶために、過去の施工実績や口コミを確認することが重要です。公式サイトやSNSで施工事例をチェックし、実際に修理を依頼した人の口コミを比較すると、業者の対応や仕上がりの質が分かります。特に地元密着型の業者は地域での評判が良く、実績が豊富なことが多いため、周囲の評判も参考にするとよいでしょう。
保証やアフターサービスの内容を確認する
修理後に再び雨漏りが発生した場合の対応を考え、保証やアフターサービスの内容を確認することが大切です。修理後の保証期間が最低でも1年以上あるか、定期点検や追加補修の対応が含まれているかを事前にチェックしましょう。特に谷樋の交換や補修を行った場合は、数年後の劣化状況を点検してもらえるかどうかも重要なポイントです。
まとめ
屋根の「谷」や「谷樋」は、お住まいの排水機能の要となる大切な部分です。建物を長持ちさせ、快適に暮らすためには、これらの部分をしっかりと手入れすることが欠かせません。雨が降ると大量の水がここに集まってくるため、年月が経つにつれて傷んだり、落ち葉やゴミが詰まったりして雨漏りの原因になりやすいのです。そのまま放っておくと、建物に大きな被害が出る可能性もあります。そのため、専門家による定期的な点検を行い、問題が見つかった際には早めに修理することをお勧めします。
さいたま市で谷樋の修理や点検をご検討の方は、豊富な経験と確かな技術を持つウェルスチールまでお気軽にご相談ください。